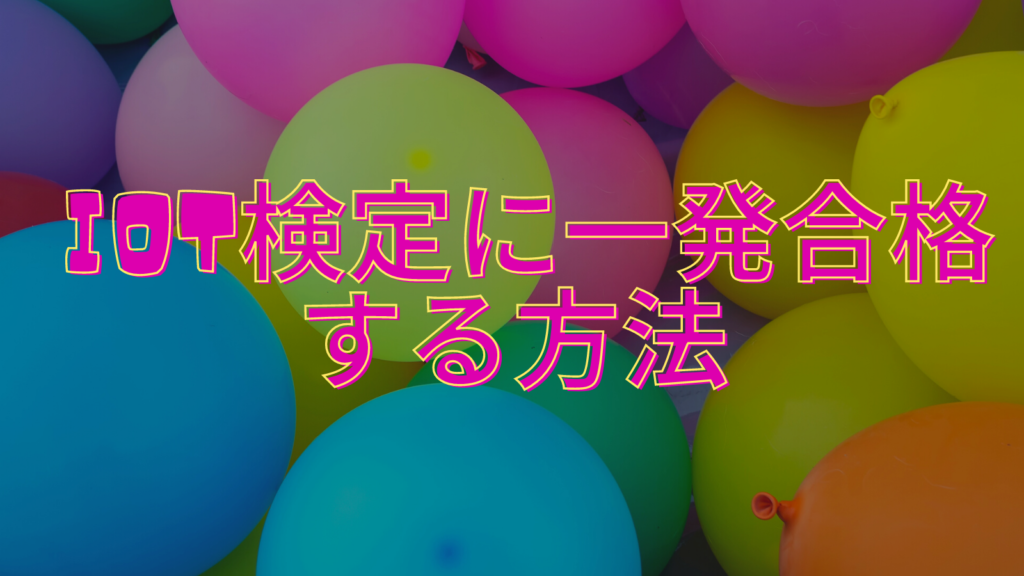
こんにちは🌞IT営業マンです!
今回のブログは筆者が先日受験した【IoT検定レベル1 プロフェッショナルコーディネーター】についてです!
IoT検定レベル1 プロフェッショナルコーディネーターの詳細はこちら
2021年8月にIot検定レベル1プロフェッショナルコーディネーターに見事一発合格することができましたので受験体験記をブログにします。
受験結果は100点満点中77点で合格することができました。
受験後の感想は「難しかった‥。。落ちたかもしれん(T . T)」でした。そのため合格の結果が出たときは結構喜びました笑
IoT検定はIT系資格ではよくあるCBT方式のため試験後に自分の回答の正否が不明であり,過去問もありません。
そのためIoT検定を受験しようと試みてもどのように勉強をすればいいか迷ってしまう方もいるでしょう。
そのような方にIoT検定レベル1の合格者である筆者がどのように勉強に取り組んだかを説明します!
IT営業マンのプロフィール・・・

IT企業の営業職
IoT分野だとネットワーク分野が専門領域
その他項目は1から勉強
勉強期間は1日2〜3時間程度で約2ヶ月でした
IT企業には勤めていますがIotに触れることは95%くらいないためほぼ初心者です。しかし、今後絶対にIotの知識は身につけておいて損はない!と考えたため受験するに至りました。
IoT検定は公式参考書が販売されています。筆者は公式参考書でしか学習していません。
IoT検定を受験するには必須の参考書です。
この記事でわかること
- IoTとは
- IoT検定とは
- IoT検定の出題範囲
- IoT検定の勉強方法
- IoT検定は難しい!?
IoTとは?
IoT検定と言いますがIoTとは何でしょうか。

IoTという端末があるの?
IoTっていうのは商品の名前?それともブランド?
IoT・・・Internet of Things
直訳すると【もののインターネット】です。
【もののインターネット】だけでは意味がわからない日本語です。
さらに詳しく説明するとあらゆる物がインターネットにつながることです。
そのような概念を【IoT】と呼びますのでIoTという商品がある訳でもなければIoTというブランドもありません。
物がインターネットにつながっていることをIoTと呼びます。
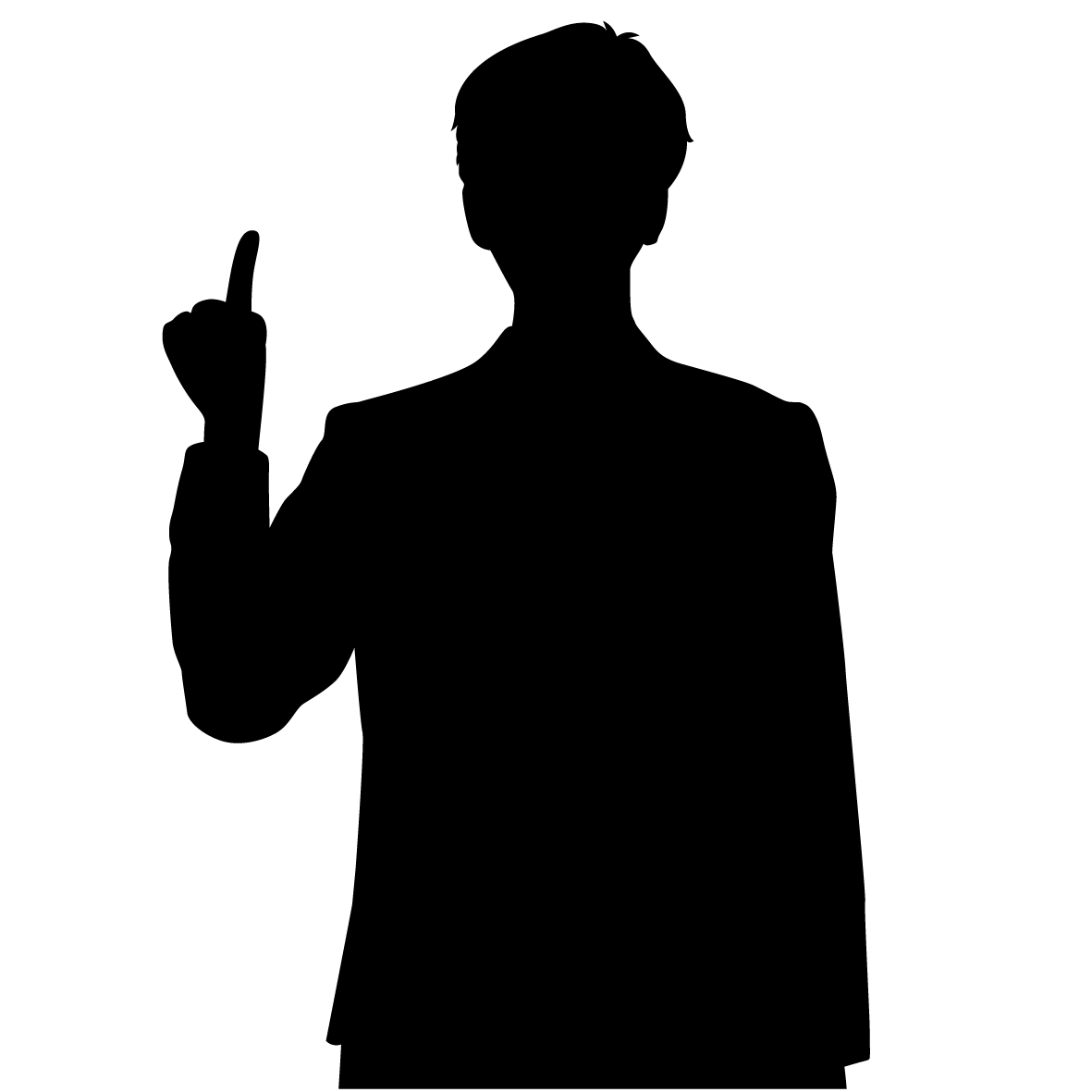
家電製品の操作をスマホから行ったり,農業において温度管理を自動で行ったりする技術がIoTだよ!
IoT検定とはそのようなIoTについての知識を証明する資格です。
IoT検定はマネジメントや基本的な要素も含まれるのでガチガチなエンジニア向けというよりはIoTを販売する人向けの内容な印象です。
似た資格にIoTシステム技術検定がありますがこちらがエンジニア向けの資格な印象です。
IoT検定の出題範囲
上記でIoTについての概要を説明しました。
IoTとは【あらゆる物をインターネットに繋ぐこと】でしたので例えばデバイス1つだけでは実現できません。
インターネット通信機能を持つデバイスを通信する仕組みやそのデバイスから得たい情報をどのように取得するのか方法を知っておかなければいけません。
そのためIoT検定ではIoTを上手に利用するために知っておかなければならない知識や営業として提案する際に知っておきたい知識が試されます。
IoT検定を学習するにあたって公式参考書が販売されています。
以下出題範囲は参考書に従って説明しています。詳細を知りたい方は参考書をご購入下さい。
8章構成で参考書は作られていますがそれぞれの章から平均的に出題されるのではなくIoTを考える上で重要な部分が多く出題されます。
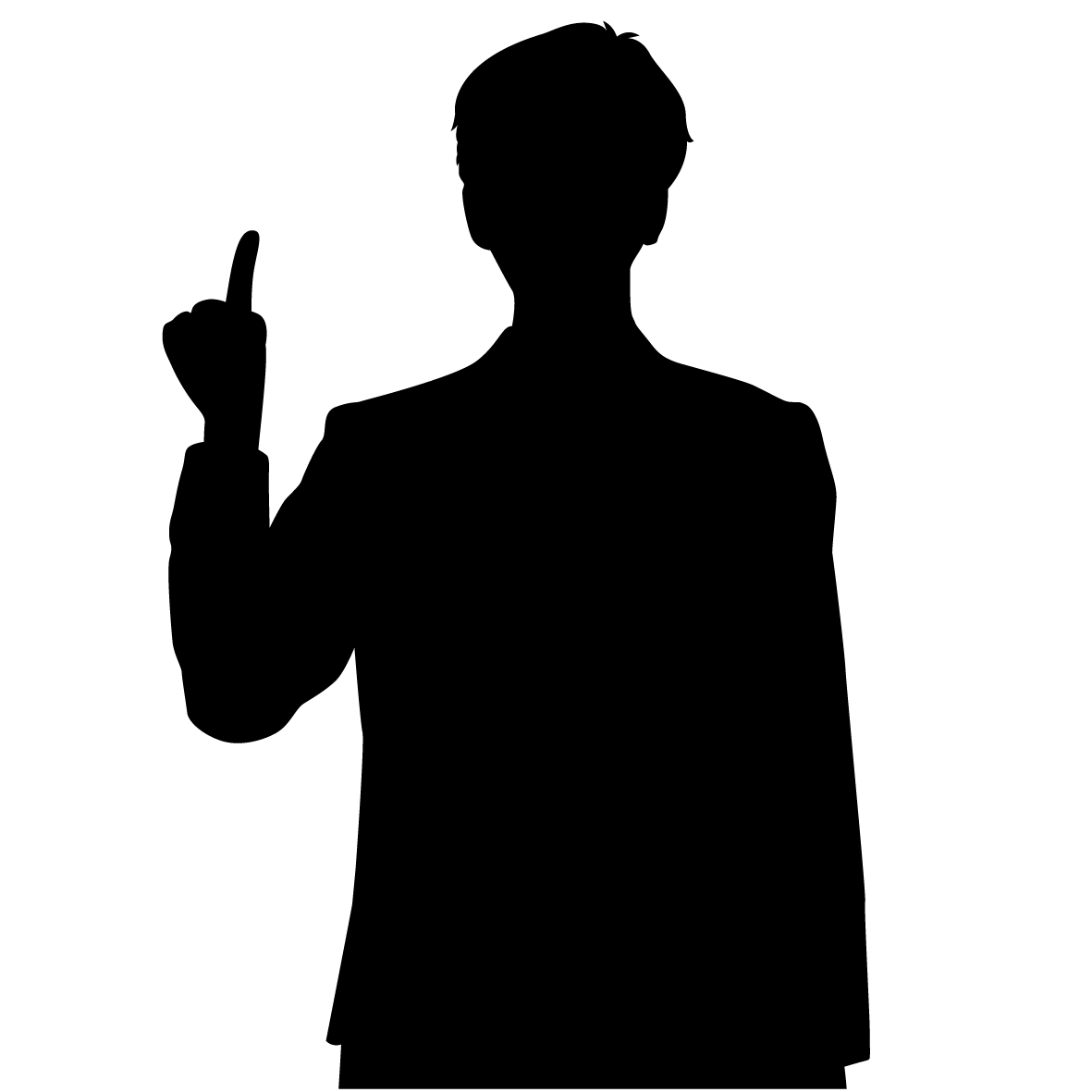
4章以降が重要項目だよ!
その中でもネットワーク,デバイス,データ分析,セキュリティ
は出題が多い印象だったよ!
戦略とマネジメント
1章は【戦略とマネジメント】です。
戦略とマネジメントとは企業の成長戦略のような章です。
IoTの仕組みとは直接の関わりはあまりない項目ですが企業でIoTを利用する立場になった時,自社の方針に基づいたIoTの利用を考えることができます。

うーん…
無理くり理由をつけた感じだなあ〜💦
この章はIoTだからということではなく企業経営を考える立場なら必須となる知識だよ。
具体的には【ファイブフォース分析】や【セル生産方式】,【アンゾフの成長戦略】など企業経営する方が身につけておくべき必須スキルを説明しています。
IoTを導入検討する方は1社員ではなく,企業の上層部だろう。という考えからこの内容も参考書で説明されているのではないかと思います。
IoTだからこその内容では無いためこの範囲からの出題数は少ないです。
IT系の入門スキルである【ITパスポート】を持っている方ならノー勉でもこの章はクリアできると思います。
産業とシステム
2章は【産業とシステム】です。
この章も題名だけではどんな内容が出題されるのか分かりにくいです。
出題数もそれほど多くありません。
産業とシステムでは今までの時代でITがどのように進化してきたのか,現代ではITについてどのように考えられているのか等が問われます。
具体的には【産業革命】や【スマートシティ】,【インダストリー4.0】などです。
この章も半分はITパスポートとかぶります。その他の内容も難しい内容ではないので用語を覚えておけば試験は全く怖くありません。

私はこの章の正答率が1番悪かったです^^;
回答の正答はわからないのでどれを間違えたのかわかりませんが悩んだ記憶はなかったのでこの章の正答率が1番悪かったことは予想外でした。
皆様はこの章は覚えれば良いだけなので筆者のような結果にならないようにしてくださいね!!
法律
3章は【法律】です。
法律と行っても六法全書を読んで把握しなければいけないとかそんなたいそうな内容ではありません。Iotを運用するにあたって関わってくる法律に関することを問われます。この章も受験した感覚としてはそこまで出題数は多くなかったのではと記憶しています。
具体的には【電波法】【周波数の使用】などもの同士を通信するために使用する電波や周波数について基本的に知っておかなければならないことが問われます。
参考書を読んでこんな決まりがあるんだ程度に頭に入れておけば問題ない項目かなと考えています。
ただしその中でも【個人情報に関する部分】は重要になってきますのでIotを利用して個人情報のやりとりを考えている方はしっかりと身につけておかなければいけません!
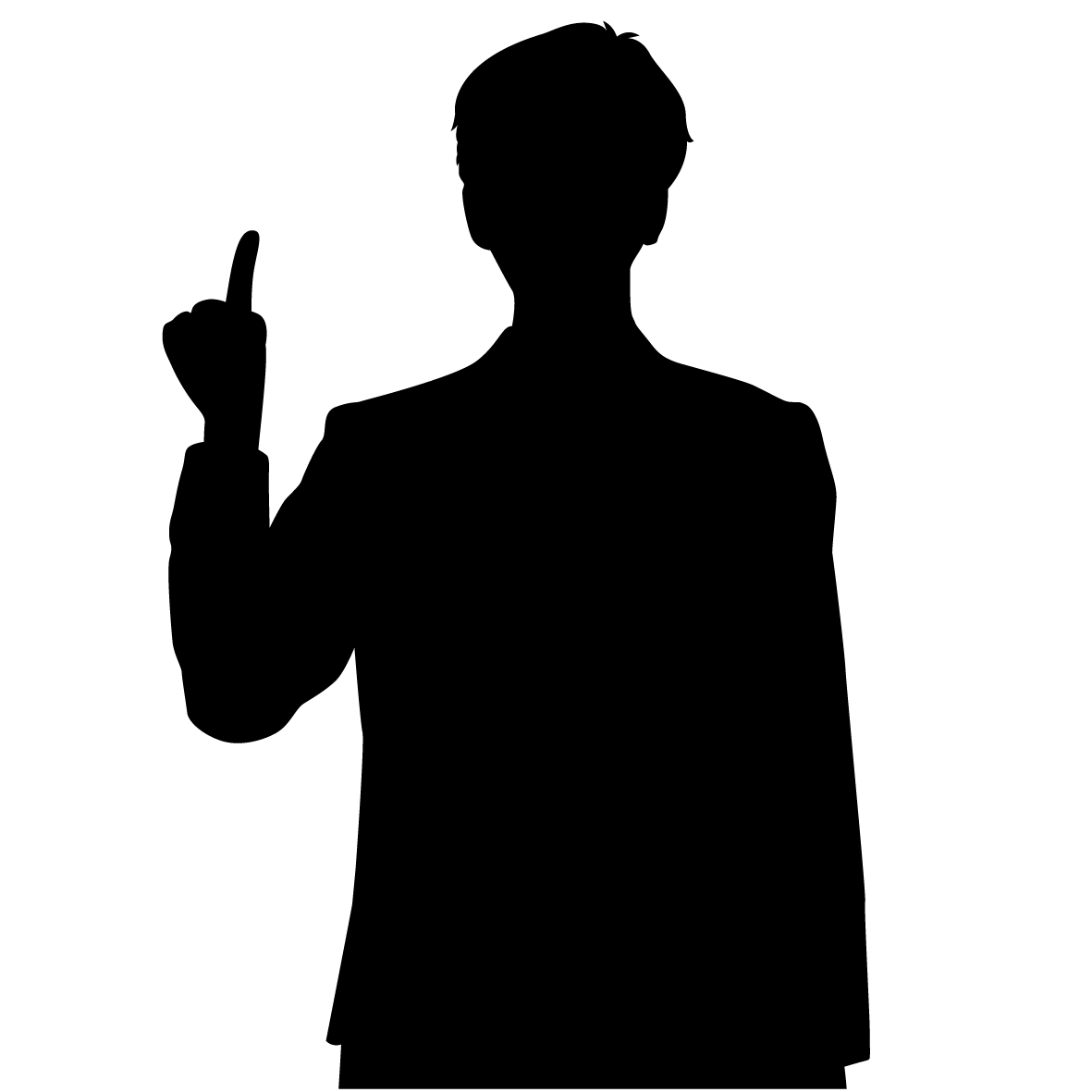
特に海外の情報を扱う場合はその国の法律に基づいてになるのでしっかりと知識をつけておかなければいけないよ!
ネットワーク
4章は【ネットワーク】です。
知識ゼロからスタートするとこの辺りから少々辛くなります(^◇^;)
初めにも記載しましたが4章以降がIotに関わるにあたって重要な項目になってきます。そのため試験でも出題範囲もこの章以降の内容の方が断然多いです。
ネットワークとは抽象的な言葉ではありますがIotにおいてモノとモノをつなぐための道のことです。ネットワークを構築しなければモノがあってもモノとモノがつながることはできません。つながらなければIotの概念が崩壊してしまいます。ただのモノです。

ただのモノだったら今の生活で使用している今までのモノと何も変わらないもんね。
モノとモノが通信するから生活が楽になるんだよね!
ではモノがモノとどのように通信するのでしょうか。その方法や場所や用途、頻度によって山ほどあります。その辺を学習するのが4章のネットワークです。
具体的には【Wi-Fi】や【Bluetooth】などを活用してモノとモノを接続して通信を行います。筆者ははじめにも書いた通りネットワーク関係の仕事をしていますのでこの章は馴染みがありました。
ゼロからスタートすると難しい内容ではありますがわかると楽しい内容なのでぜひ時間をかけてでもモノとモノがつながる仕組みを理解してみてください!
デバイス
5章は【デバイス】です。
この章が1番ボリューミーです。なおかつ筆者体感で1番意味がわからない項目で試験にも1番問題が出題されていた記憶があります。
4章でモノとモノがつながる仕組みは理解しました。この章ではモノ(ハードウェア)がどのように作られているのか、どのように動作しているのかを把握する項目です。
何度も言います。「何度参考書を読んでも意味がわからない!」
元々物理的なものというかハードウェアの仕組みが苦手だった筆者には絶望的な内容でした。具体的にはラズベリーパイやアルデュイーノを使ってICを埋め込みコンピュータを作るだとかモーターなどを使って自分の意図しているモノを作るといった内容です。
それらモノを作るためにどのようなコンピュータ内通信が必要かどのような電気回路が必要かなどモノを作るための知識を求められます。しかも参考書の中で1番ページ数も多いです。
一つ一つの機器と構造、仕組みまでを完璧に覚えようとするとおそらく気力が持ちません。実際に試験に合格した筆者も表面上だけ理解をしたにすぎません。そのレベルで試験で出題される問題には答えられるレベルになると思いますがしっかり理解をしたいかた‥応援しますので頑張ってください!!

この章の内容をペラペラ話す人こそ技術屋さんだからかっこよく見えるよね!
プラットフォーム
6章は【プラットフォーム】です。
プラットフォームという言葉だけ聞くとまたハードウェアか!?と思ってしまいそうですが物理的な機器のことではありません。
5章でモノの知識、4章でデータを通信する知識をつけましたので6章以降は得たデータをどのように利用するかに焦点が置かれています。

これ以降がIotの肝になるデータ活用だね!
勉強してて楽しいと感じる部分じゃないかな!
モノで得たデータを活用する観点から6章のプラットフォームではまずデータをどのように収集するか管理するかを学習する項目です。
具体的には【クラウド】や【データベース】のことを学習していきます。
あらゆるモノとモノを接続するわけですからデータにもあらゆる種類のデータがあります。データによってどのように管理をすれば良いのかこのデータどのような方法で収集するのが適しているのかなどが試験では問われます。
この章はそこまで難易度は高くないかなと筆者は感じました。
データ分析
7章は【データ分析】です。
6章で得たデータの管理方法の知識をつけました。7章では人工知能を使ってデータを分析する内容の学習です。ボリューミーな章ではありますがデータの分析手法が複数あるだけで内容自体の難易度はそこまで高くはありません。
データの種類、得たデータからどのような情報を得たいかによって分析手法を選んでいきます。この章では自分が得たい情報を得るためにどのようにデータを分析するかを学びます。
Iotはモノとモノが通信することですがモノ同士が通信することが目的ではありません。ではIotの目的は?というとモノとモノが通信することで人が定期的に訪れなくてもあらゆるデータを収集すること、人間が分析するには膨大すぎるデータをサーバに取り込むことです。
そうすることによって今まで発見することができなかった相関性や新たな価値を見出すことが可能になります。その考えを前提にすると7章のデータ分析はIotにとって非常に重要な項目になります。

データを得るとか考えずにモノとモノを通信させて操作するなどモノとモノの通信が目的になっていることもあるけどね!
筆者はだいぶ断定したね👊
資格取得が目的であれば表面上で理解しておけば良いと思いますが実務でIotを使うことを検討している方はデータ分析の知識をしっかりと身につけておきたいところです。
セキュリティ
8章は【セキュリティ】です。
セキュリティは今どの分野のIT試験でも必ず問われる項目になっています。かつ基本的に押さえておかなければならない内容はどの試験でも同様です。
Iotは端末数が膨大にありモノ単体では意味のある情報になりづらいことからセキュリティが疎かになりやすいことが問題視されています。なぜならIotの端末を踏み台にしてDDos攻撃などに用いられることがあるからです。
端末数が膨大なだけにDDos攻撃にも大きな影響をもたらします。そのためIot機器のセキュリティ対策は非常に重要な項目になります。
この章の内容は必ず身につけた状態で試験に臨むようにしてください!
IoT検定の勉強方法
では、ここからIoTの実務経験ゼロの筆者がどのように勉強をして試験に臨んだのかお伝えします!
筆者が行った勉強方法はただひたすら【参考書を読む】、読み終わったら【問題集を解く】です!
- 参考書を読む、1周目(内容は分からなくてもいい。どんなことが書いてあるのか把握するため)
- 参考書を読む、2周目←1番時間がかかった(内容を理解しながら読む。分からない言葉はググって内容を理解することに尽力する)
- 問題集を解く、1回目(解いたら全問解説を全部読む)
- 参考書を読む、3周目(基本流し読み。問題集で間違えたところ、問題集で出て来たところ、これなんだっけ?となったとこだけ再度理解できるように読む)
- 問題集を解く、2回目(なぜ正解なのか、他の回答はなぜ間違いなのかを説明できるようにする)
以上が筆者が行った勉強法です。
IoT検定に限らず筆者が何かを勉強する時はこの順番で行うことがほとんどです。時間はかかりますが確実に身につけることができます。
問題集は絶対に買った方がいいです!参考書だけでは知識習得がどれくらいできているのか判断する基準がありません。IoT検定の資格取得を目指している方はぜひ問題集も購入することを オススメします。
試験は資格を取ることが目的で受けるわけではありません。(という方もいると思いますが‥)試験は検定で証明されるスキルを実務で活かすために取得するのです!資格を持っていても実務で役に立たなければ意味がありません。
IoT検定、振り返ってみると初めて目にする言葉が多く何度も言いますが5章のデバイスはとっても大変でした。勉強法2番がいつになったら終わるんだろうと感じました。。
知識ゼロからスタートする方は時間はかかるかもしれませんが参考書と問題集に取り組めば実務経験はなくとも間違いなく資格は取得できます。
途中で壁にぶち当たってしまう方もぜひ諦めずに勉強を進めてみてください!!
このブログを読んでいただいた皆様も一発で試験に合格できることを願っております!
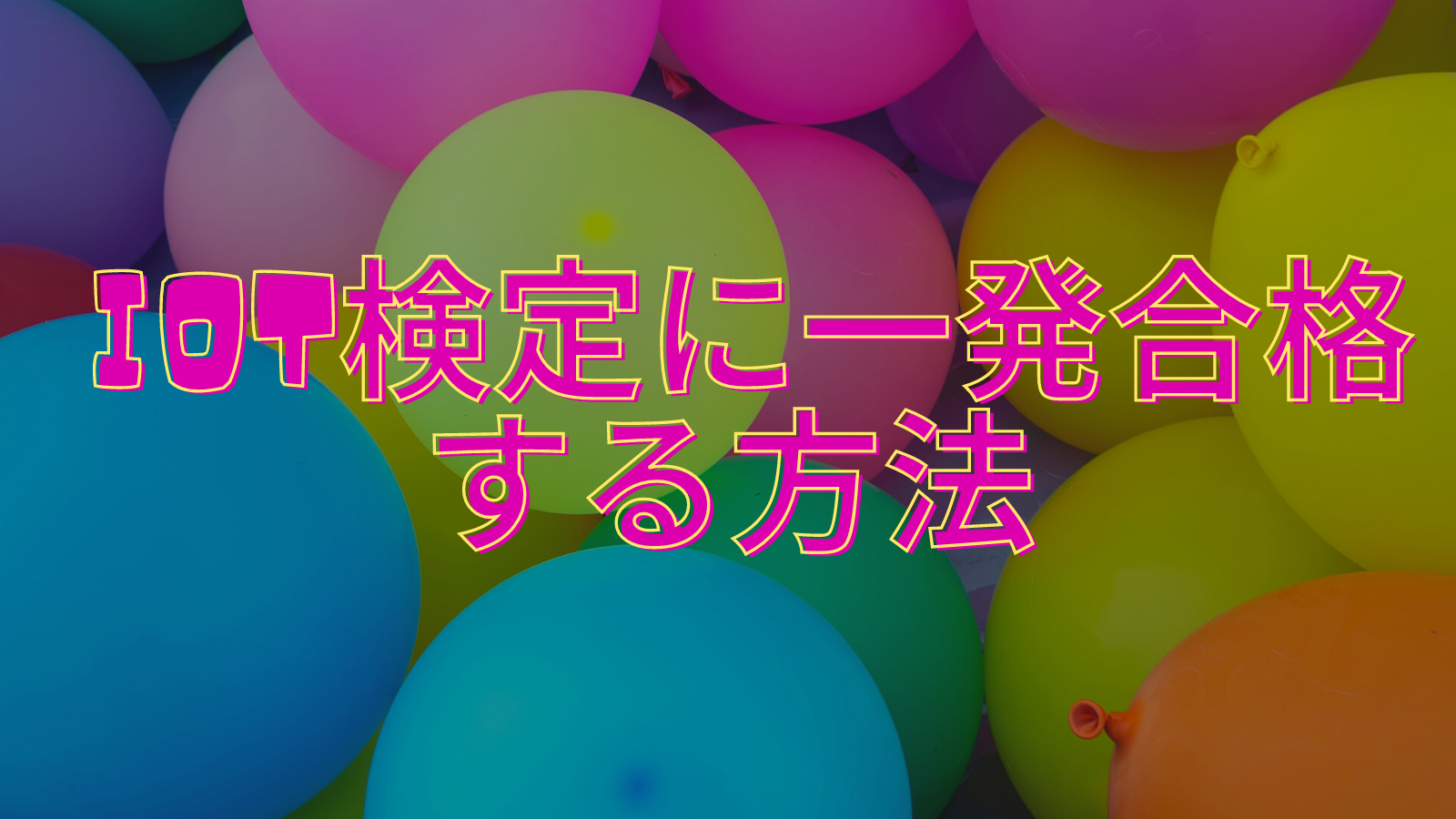


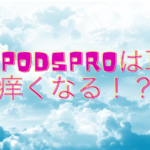

コメント